
カテゴリー
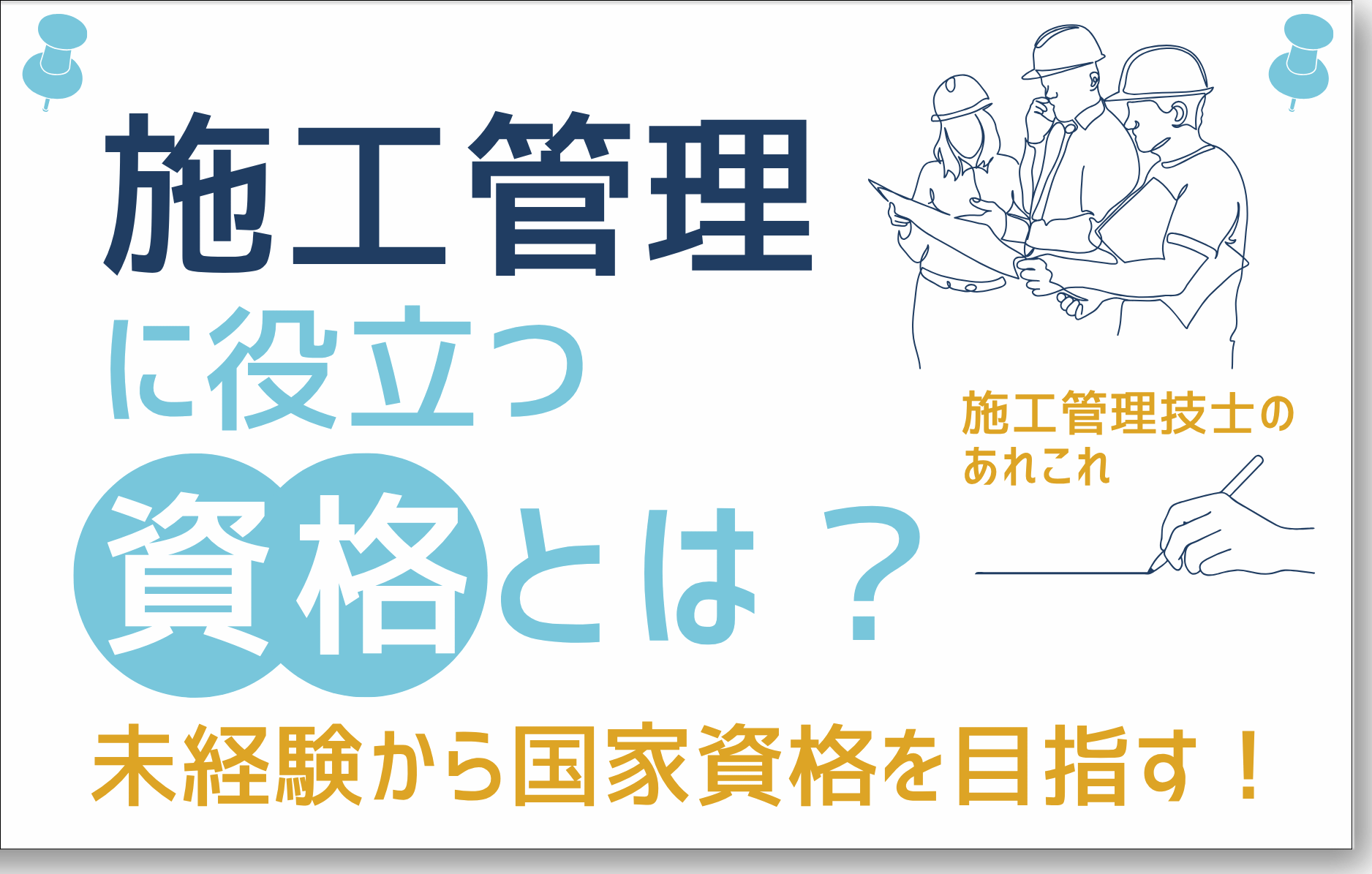
施工管理は資格で差がつく!
未経験から国家資格を目指す方法
「施工管理って何をするの?」「資格がないとできないの?」そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、施工管理の仕事内容から資格の種類、未経験から資格取得を目指す道筋まで、わかりやすく解説していきます。
今の仕事にモヤモヤを感じている方や、「手に職をつけたい」と考えている方にも役立つ内容です。
この記事でわかることをチェック!
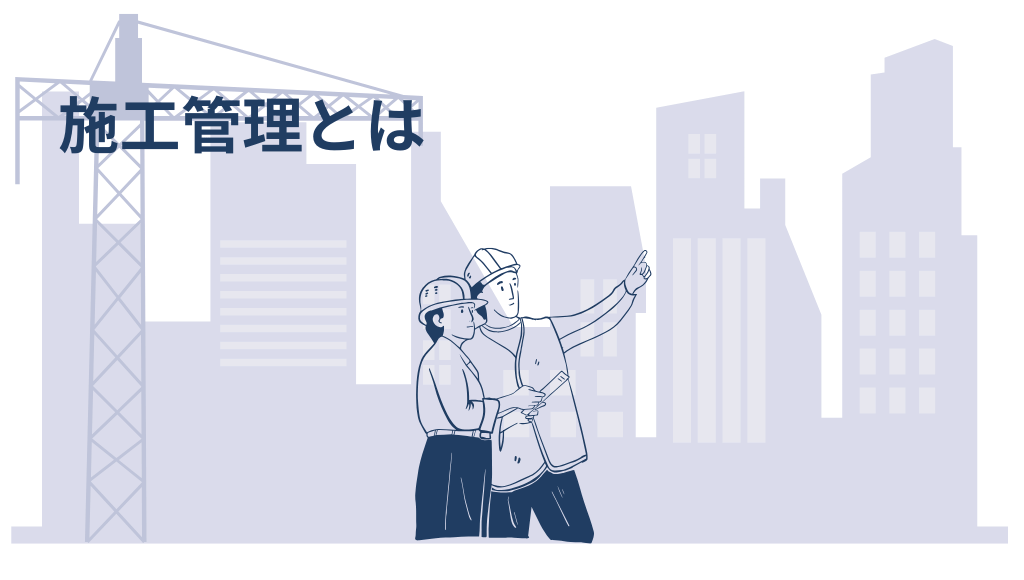
施工管理に興味はあっても、「具体的に何をするのか」「資格は本当に必要なのか」がわからない方も多いかもしれません。ここでは、施工管理の基本と、資格が重視される理由を紹介します。
施工管理とは、工事現場における「工程」「品質」「安全」「原価」「環境」の5大管理を行う仕事です。建築・土木・電気・設備などの分野で、工事がスムーズかつ安全に進むよう、全体の進行をコントロールします。
具体的には、資材の発注、職人さんへの指示出し、スケジュール管理、現場の安全確認、書類作成など多岐にわたる業務を担います。現場とオフィスの両方で働くことが多く、まさに現場の司令塔というイメージです。
施工管理の仕事を担う上で、一定の規模以上の工事では「施工管理技士」の国家資格が必要になります。これは建設業法に基づき、現場における有資格者の配置(主任技術者・監理技術者)が義務付けられているためです。
施工管理技士には「1級」と「2級」があり、工事の規模や管理範囲、任される役職によって求められる等級が異なります。
また、建築・土木・電気工事・管工事など、工事の種類ごとに資格が分かれており、自分の志望する業界に合った資格を目指すことになるでしょう。
施工管理において資格が求められるのは、法律面だけが理由ではありません。
公共工事や大規模な建築物など、社会的責任の重いプロジェクトでは、専門的な知識と技術を持った人材が不可欠です。国家資格である施工管理技士を取得することで、そうした専門性と責任を証明できるのです。
また、資格試験では「工事計画」「安全管理」「施工技術」などの知識だけでなく、マネジメント力や法令知識も問われます。そのため、計画性・リーダーシップ・冷静な判断力・調整力といった資質がある人は、施工管理でとくに力を発揮しやすいでしょう。
施工管理の就職先は多岐にわたり、建設会社や住宅メーカー、設備会社、土木工事会社など、インフラや暮らしに関わるさまざまな業界でニーズがあります。
さらに新築住宅の施工やリフォーム工事、道路・橋などの土木インフラ整備、電気・空調といった設備工事など、自分の興味やライフスタイルに合わせた分野を選べるのも魅力です。
また、未経験からスタートできる企業も多く、資格取得をサポートする制度を整えている会社もあります。Mivooのような転職サポートサービスを活用すれば、自分に合った環境でステップアップを目指しやすくなるでしょう。
\ LINEで適職診断 /
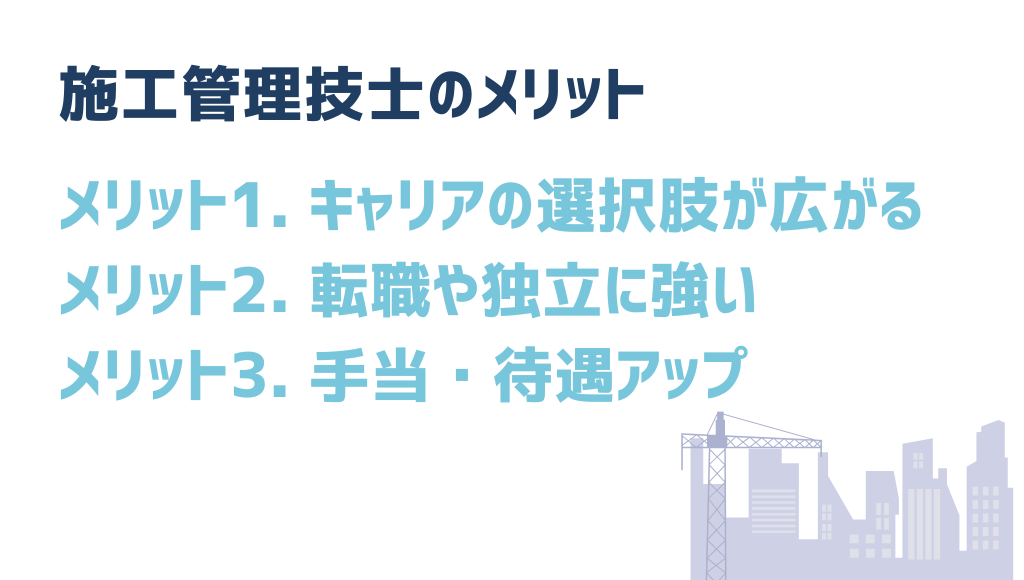
施工管理の仕事は、資格がなくても一部関わることはできますが、やはり国家資格を持っているかどうかでキャリアの選択肢や待遇には大きな違いが出ます。
施工管理技士の資格を取得することで得られる具体的なメリットを確認していきましょう。
施工管理技士を取得することで、年収・役職・仕事の幅すべてが広がります。
2級の合格で「主任技術者」、1級を取得すれば「監理技術者」として現場責任者に抜擢されるケースも増えます。役職が上がることで当然給与にも反映され、年収600万円以上を狙えるポジションに就くことも現実的です。
また、資格を持つことで公共工事や大規模プロジェクトに関われるようになるため、スケールの大きな仕事に挑戦したい人にとっても有利です。
施工管理技士の資格は、転職市場において非常に高い評価を受けます。
施工管理の有資格者は建設業界のどの分野でも需要が高く、業界内で引く手あまたの存在になるでしょう。中途採用でも即戦力として歓迎されるため、希望する職場への転職がしやすくなります。
さらに、実務経験を積んでいけば、独立して個人事業主やフリーランスとして働く選択肢も広がります。 自分の裁量で働きたい人や、専門性を活かして自由にキャリアを築きたい人にとっては、大きな武器となるでしょう。
施工管理技士の資格を取得すると、所属企業からの待遇が目に見えて向上することも少なくありません。
資格手当が支給される企業は多く、月1万〜3万円の手当や、賞与への加算、昇進の加点などに直結します。また、会社によっては受験費用や講習代を補助してくれる制度を設けているところもあります。
企業側にとっても、法的に必要な「資格者の配置」ができることは大きなメリット。そのため、資格取得者を積極的に支援し、社内でも厚遇する傾向があります。
\ LINEで適職診断 /
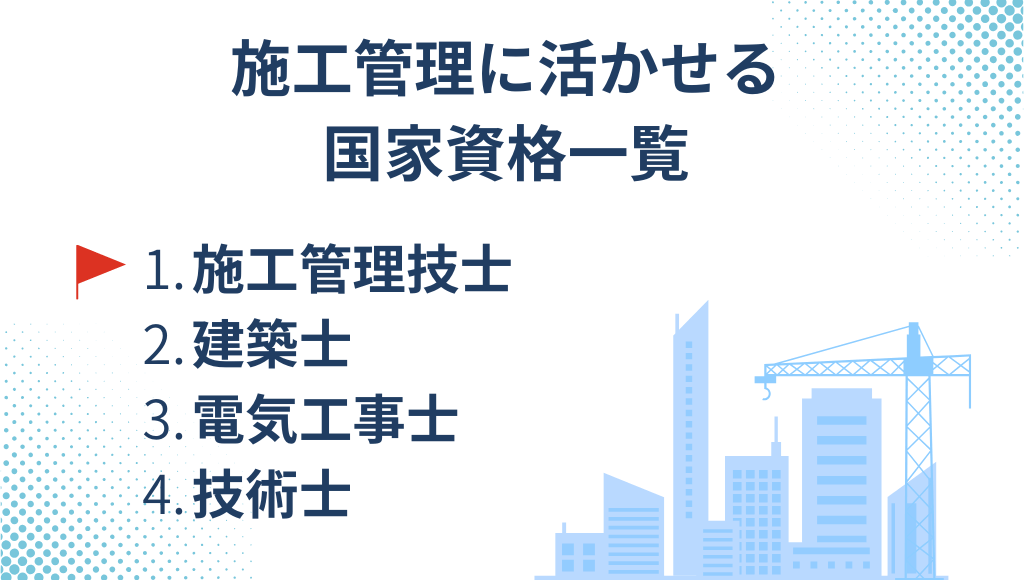
施工管理の仕事を本格的に行うには、一定の現場経験とともに、国家資格の取得が大きな武器になります。さまざまな資格の特徴・難易度について紹介します。
施工管理技士は、現場の責任者として配置されるために必要な国家資格です。建設業法に基づき、一定規模以上の工事には「主任技術者」「監理技術者」としての有資格者が必須とされています。
この資格には1級・2級があり、管理できる工事の規模や内容、現場での役割も異なります。たとえば、1級は大規模工事や公共工事の現場での責任者として、2級は中小規模の現場や補佐的な立場として活躍することが一般的です。
また、施工管理技士は業種別に7つの種類があり、自分の進みたい分野に応じた資格を目指す必要があります。
【7種類の施工管理技士】
建物の新築・増改築・改修などを管理する資格。住宅・ビル・マンションなどが対象。民間・公共問わず案件数が多く、とくに需要が高い分野です。
道路・橋・トンネル・ダムなど、インフラ工事を管理する資格。公共工事が多く、安定性のあるキャリアパスが魅力です。
オフィスビルや工場などの電気設備工事の現場管理に必要。省エネ・再生可能エネルギー関連の需要も高まっています。
空調・給排水・冷暖房・ガス配管・衛生設備など、水と空気に関わる工事を管理。住宅から大型施設まで幅広く活躍できます。
ショベルカーやブルドーザーなど、建設機械を用いた施工管理に必要。主に重機オペレーションと工程管理を行う現場に対応しています。
公園・庭園・緑地整備などの造園工事の現場を管理。植物や景観に関心がある人に人気の分野です。
通信インフラ(光回線・ケーブルTV・基地局など)に関する工事を管理。5GやIoTの普及により、今後さらに注目される分野です。
施工管理技士以外にも、現場での活躍やキャリアアップを支える資格があります。
いずれも国家資格であり、特定の分野での専門性を高めるだけでなく、施工管理技士の学習や試験に活かせる知識が身につく点も魅力です。
設計・図面に関わるイメージが強い資格ですが、建物構造や工程理解に役立ち、建築施工管理の現場でも大いに活かせます。とくに1級は高い専門性を求められるため、施工管理の上級職を目指す方にとっても強力な武器です。
電気設備の施工に不可欠な資格で、電気工事施工管理技士を目指す人にとって基礎固めにもなるものです。第1種を持っていれば、高圧設備工事にも対応できる現場で活躍できます。
高度な専門知識と実務経験を問われる理工系技術者の最上位国家資格。施工管理技士の先に目指すキャリアのひとつとして位置づけられます。合格すれば、将来的に設計・管理・技術指導の中核的役割を担う存在となれます。
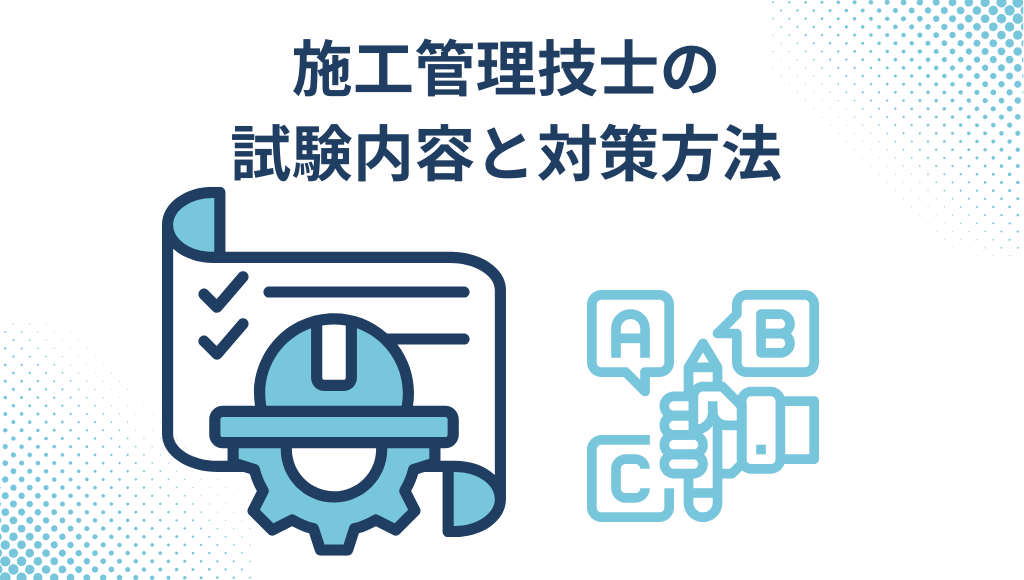
施工管理技士の資格を取得するには、計画的な試験対策が欠かせません。とくに、二次検定では実務経験を言語化する力も問われるため、事前の準備とスケジューリングが合否を分ける鍵となります。
施工管理技士の試験は「一次検定」と「二次検定」に分かれており、令和6年(2024年)から受験資格のルールが大きく変わりました。ここでは、建築施工管理技士を例に解説していきます。
受験年度末時点で19歳以上
受験年度末時点で17歳以上
⇒ 年齢条件を満たせば、学歴や実務経験がなくても受験できます。
一次検定に合格したうえで、下記いずれかの条件を満たす必要があります。
└ 実務経験5年以上
└ 特定実務経験を含む実務検定3年以上
└ 監理技術者補佐としての経験が1年以上
└ 実務経験3年以上(建設機械は2年以上)
└ 1級一次合格+実務経験1年以上
※分野により詳細は異なるため、施工管理技術検定公式サイトの確認をおすすめします。
└ 一次検定:36.2%(2024年実施)
└ 二次検定:40.8%(2024年実施)
└ 一次検定:45.0%(2025年前期実施)
└ 二次検定:40.7%(2024年実施)
建築施工管理技術検定の合格基準は、一次検定・二次検定ともに60%以上です。
2級よりも1級の方が難易度が高く、試験範囲の広さや記述力の精度がより厳しく求められます。
施工管理技士の試験は、「一次検定」と「二次検定」の2段階で構成されています。
出題形式:マークシート形式
主な出題範囲:施工計画、品質・工程・安全管理、建築法規、構造、設備など
出題形式:記述式が中心
主な出題範囲:実務経験をベースに記述、用語説明、工程表、法規、施工
一次検定はマークシート形式の知識試験のため、比較的取り組みやすい傾向があります。
一方、二次検定では実務経験に基づく記述式問題が中心のため、経験の浅い方にはやや難関と感じられるかもしれません。
ただし、一次検定に合格していれば、翌年度以降は二次検定のみの受験が可能です。
1級施工管理技士の合格には、合計で300〜500時間程度の学習時間が必要とされます。働きながら挑戦する方も多いため、効率よく進める工夫が大切です。
【勉強時間の目安】
一次検定対策では、施工管理全般の知識や建築法規、関連法令などを重点的に学びましょう。インプットを終えたら、過去問を繰り返し解くことで、理解の定着と出題傾向の把握に繋がります。
二次検定対策では、経験記述のテンプレートを作成し、模範解答を参考に表現力を磨くことが重要です。添削サービスなども活用することで、記述の質を高めることができます。
2級施工管理技士の勉強時間はこちらをチェック

「Mivoo」は、
20代転職をサポートする
”転職エージェント”です!
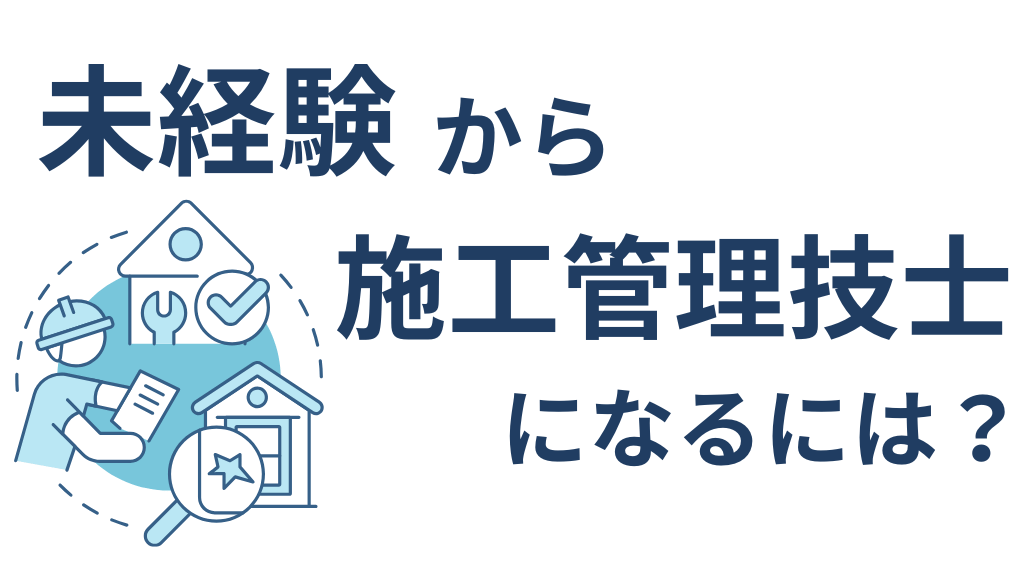
「施工管理の仕事に興味があるけれど、資格も経験もない…」そんな方でも大丈夫です。
実は、施工管理の仕事は資格がなくても始められるケースが多く、未経験からスタートして、働きながら資格取得を目指す人もたくさんいます。
施工管理の仕事は、未経験・無資格からでもスタート可能です。多くの企業では人手不足を背景に、「アシスタント」として現場に入ることが一般的。たとえば、写真撮影・書類作成・工程チェックなどの補助業務を通して、実務を学んでいけます。
また、資格取得支援制度を導入している会社も多く、働きながら資格を目指すことも十分可能です。
施工管理技士の受験には、一定の実務経験年数が必要です。まずは補助業務や現場アシスタントとして経験を積み、1〜5年ほどで2級の受験資格を得られるのが一般的です。
未経験からでも、現場での経験を重ねることで確実にキャリアを築いていけるのが施工管理職の魅力といえるでしょう。
\ LINEで適職診断 /
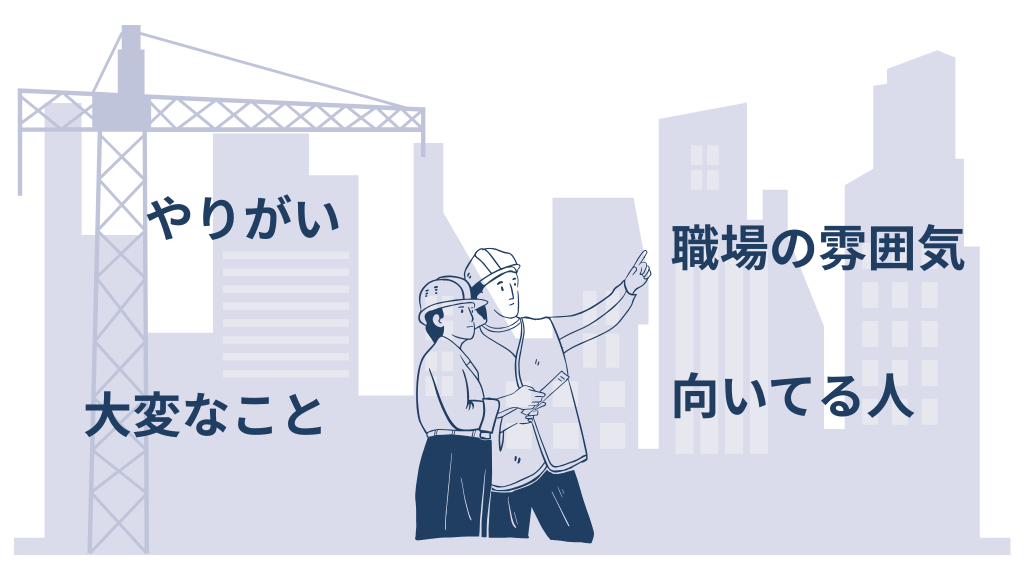
施工管理って、どんな仕事?実際の働き方はどうなの?
そんな疑問を持つ方のために、現場のリアルな声や働き方の特徴をまとめました。
施工管理の仕事は、建物やインフラが形になっていく過程を、最前線で見守れるやりがいのある職種です。自分が携わった建物が完成し、街の一部として長く残ることに、誇りや達成感を感じられる人も多いでしょう。
一方で、工期や工程の管理、人との調整などが日々発生するため、プレッシャーやストレスを感じる場面も。職人さんや関係者とのコミュニケーション、スケジュールのすり合わせが苦手な人には、大変だと感じることがあるかもしれません。
施工管理の現場では、学歴よりも実務経験や資格取得の意欲が重視される傾向があります。実際に、高卒でアシスタントとして現場に入り、経験を積みながら2級施工管理技士の資格を取得し、正社員として活躍している人も少なくありません。
Mivooでも、「高卒OK」や「資格取得支援あり」の求人を紹介しています。未経験からでも着実にキャリアを築けるのが、この業界の魅力のひとつです。
20代特化の転職エージェント
施工管理の仕事には「体育会系」「上下関係が厳しい」といったイメージを持つ方もいるかもしれませんが、最近は若手や女性の活躍も増え、風通しの良い現場も増えています。
とくに、未経験者を育てる文化のある会社では、丁寧に教えてもらえる環境が整っていることも。初めての職場で不安な人は、教育体制や社員の年齢層などにも注目して求人を選ぶと安心です。
施工管理の仕事に向いているのは、次のようなタイプの人です。
一方で、環境の変化が苦手な人や、マルチタスクが苦痛に感じる人、極端に人と話すのが苦手な人には負担が大きいかもしれません。
とはいえ、自分の得意を活かせる現場や職場環境を選ぶことで、無理なく働けるケースも多くあります。事前に仕事内容や職場の雰囲気を把握することが、ミスマッチを防ぐ第一歩です。
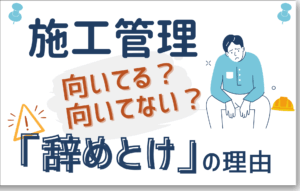
\ LINEで適職診断 /
施工管理は、「モノづくり」の最前線で働けるやりがいのある仕事です。高卒・未経験でもチャレンジ可能で、資格取得を目指しながらキャリアを築けるのが魅力です。
一方で、スケジュールや人との調整が多く、向き不向きが出やすい職種でもあります。だからこそ、事前に仕事内容や現場の雰囲気を知っておくことが、長く続けられる仕事選びのカギになります。
Mivooでは、未経験から施工管理を目指す方に向けて、資格支援あり・高卒OK・現場の雰囲気がわかる求人をご紹介しています。自分に合った働き方を一緒に見つけていきましょう。
未経験からの転職を叶えるなら‼
こんなサポートが受けれる!
未経験に特化した履歴書作成や面接練習などの選考対策!
40,000件の求人からあなたに合った企業が見つかる!
いつでも、どこでもLINEや電話で相談できるから安心!
コメント